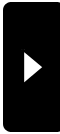2015年02月11日
風呂場の大改修に着手 裏の雨戸も修繕
2/11、山本さんと野木村さんが、いよいよ、風呂場の大改修に着手してくれました。
実は、もともとあった風呂場はとても狭く、体を洗うスペースや脱衣スペースがありませんでした。

そこで、風呂の壁をぶち抜いて隣の物置スペースと合体させ、新しい壁で多い、地面はコンクリートを打つという計画を、2人は立てたようです。
「壊し屋」との異名をとる山本さんが、さっさと壁をぶち抜きましたが、当然のように大量の廃材が発生。それを片付けて、さらに地面を均したら、もうタイムリミットが迫っていたので、本日はそれで終了!残りの作業は、後日、行うそうです。
*スイマセン!写真がありません!
なお、滑りが悪く、戸袋も壊れていた裏の雨戸は、野木村さんがチョチョイと直してくれました。

実は、もともとあった風呂場はとても狭く、体を洗うスペースや脱衣スペースがありませんでした。

そこで、風呂の壁をぶち抜いて隣の物置スペースと合体させ、新しい壁で多い、地面はコンクリートを打つという計画を、2人は立てたようです。
「壊し屋」との異名をとる山本さんが、さっさと壁をぶち抜きましたが、当然のように大量の廃材が発生。それを片付けて、さらに地面を均したら、もうタイムリミットが迫っていたので、本日はそれで終了!残りの作業は、後日、行うそうです。
*スイマセン!写真がありません!
なお、滑りが悪く、戸袋も壊れていた裏の雨戸は、野木村さんがチョチョイと直してくれました。

タグ :風呂
2014年06月29日
雨戸の修繕作業
6/28(土)と6/29(日)に、野木村さんご家族が大奮闘してくださり、もりの すけの家の表側の雨戸6枚を修繕することができました。
参加者は、6/28(土)は、野木村夫妻と娘さん、水谷、山本親子、仁科さん、6/29(日)は、野木村夫妻と娘さん、山本親子、間宮さん、草ヶ谷さん、水谷でした。6/29(日)の午前中は、草ヶ谷さんと水谷は清沢に行き、ブルーペリー やカボチャ・スイカ等のお世話、じゃがいも掘り、草刈りなどの作業を行い、午 後から野木村さんの工房に合流しました。
雨戸6枚の修繕ですが、まずは清沢から野木村さんの工房に運び込み、1枚ず つ慎重に解体して、腐っていた合板とトタンを取り除きました。
次に破損が激しかった下枠の部分をすべて作り直して交換、上枠も破損してい るものは作り直して交換しました(野木村さんの記述全開です!)。
割れたりりていた枠は木工用ボンドでつなぎ合わせつつ、すべての枠材を焦げ 茶色に塗装。
その後、新たらしく取り替えた合板と上下左右中の枠を組み直して、雨があた る合板の外側も焦げ茶色に塗装しました。
最後にもりのすけの家に修繕後の雨戸を搬入したのは、午後6時頃でした。
思ったとおり大変な作業量でしたが、野木村さんの腕前と段取りでなんとか2 日間で終えることができました。お手伝いいただいたみなさま、ありがとうござ いました。
ただ、塗料がなくなってしまって塗装できなかった雨戸1枚の塗装と、雨戸の 外側の塗装の重ね塗りがまだ残ってしまいましたが、後日、野木村さんが友人の 方々ともりのすけの家で「バーベキュー」?をする際に、塗っておいてくださる そうです。重ね重ね、ありがとうございます。








参加者は、6/28(土)は、野木村夫妻と娘さん、水谷、山本親子、仁科さん、6/29(日)は、野木村夫妻と娘さん、山本親子、間宮さん、草ヶ谷さん、水谷でした。6/29(日)の午前中は、草ヶ谷さんと水谷は清沢に行き、ブルーペリー やカボチャ・スイカ等のお世話、じゃがいも掘り、草刈りなどの作業を行い、午 後から野木村さんの工房に合流しました。
雨戸6枚の修繕ですが、まずは清沢から野木村さんの工房に運び込み、1枚ず つ慎重に解体して、腐っていた合板とトタンを取り除きました。
次に破損が激しかった下枠の部分をすべて作り直して交換、上枠も破損してい るものは作り直して交換しました(野木村さんの記述全開です!)。
割れたりりていた枠は木工用ボンドでつなぎ合わせつつ、すべての枠材を焦げ 茶色に塗装。
その後、新たらしく取り替えた合板と上下左右中の枠を組み直して、雨があた る合板の外側も焦げ茶色に塗装しました。
最後にもりのすけの家に修繕後の雨戸を搬入したのは、午後6時頃でした。
思ったとおり大変な作業量でしたが、野木村さんの腕前と段取りでなんとか2 日間で終えることができました。お手伝いいただいたみなさま、ありがとうござ いました。
ただ、塗料がなくなってしまって塗装できなかった雨戸1枚の塗装と、雨戸の 外側の塗装の重ね塗りがまだ残ってしまいましたが、後日、野木村さんが友人の 方々ともりのすけの家で「バーベキュー」?をする際に、塗っておいてくださる そうです。重ね重ね、ありがとうございます。








2013年08月31日
自在鉤完成!? 大根畑

囲炉裏に念願の自在鉤が付きました。間宮さんと杉山さんの力作です。
でもこの魚?、本来の鯛というよりスナメリといった感じ。もらい物だそうです。
まあ、こういうのもいいかなぁ。

先週、仁科さんが種をまいたダイコンは、芽が出てました。
2012年12月02日
トタン屋根の修理
「もりのすけの家」付近は台風でも大風は吹かないのですが、なぜか11月の台風で母屋と納屋との間のトタン屋根が吹き飛んでしまいました。
今日は、家の南西側も含めて、トタン屋根の修理をしました。

南西側のトタン屋根修理の担当は、間宮さんと仁科さんです。

ラインがそろっていませんが(わさと?)、きれいに出来上がりました。

母屋と納屋との間のトタン屋根の修理は大変でした。
まずは、古くなった根太を取り外しました。


リーダーは、大工仕事もできる建築士の山本さんです。
池谷さんと水谷さんも手伝いました。

夕闇迫る中、2時間ほどかかって完成です。
山本さん、大活躍でした。ご苦労様でした。
今日は、家の南西側も含めて、トタン屋根の修理をしました。

南西側のトタン屋根修理の担当は、間宮さんと仁科さんです。

ラインがそろっていませんが(わさと?)、きれいに出来上がりました。

母屋と納屋との間のトタン屋根の修理は大変でした。
まずは、古くなった根太を取り外しました。


リーダーは、大工仕事もできる建築士の山本さんです。
池谷さんと水谷さんも手伝いました。

夕闇迫る中、2時間ほどかかって完成です。
山本さん、大活躍でした。ご苦労様でした。
2011年12月18日
障子貼り替え作業②
12月17日(土)と18日(日)の2日間にわたって、障子の張り替え作業を行いました。
17日は、池谷さん、野木村さんご一家、間宮さんのお知り合いの草ヶ谷さん、草ヶ谷さんのお知り合いの島村さん(大川の集落支援員の方)、杉山さんの8名が、
18日は、水谷さん、間宮さん、草ヶ谷さん、山本さん親子、杉山さんの6名が参加しました。
古い障子紙を剥がして、こびりついた糊を取り除く作業に悪戦苦闘しながら、それでも2日間の作業で20枚ほど貼り替えることができました。
間宮さんのお知り合いの草ヶ谷さんが参加してくれたり、その草ヶ谷さんが声をかけてくださったのが、私たちも知っている大川の島村さんだったり、野木村さんの奥様とお子様2人が参加してくださったりと、人と人の輪が広がり、密になりました。
「清沢の家」を中心にしていろいろな可能性を予感させた2日間でした。
■12月17日(土)






■12月18日(日)








■完成




17日は、池谷さん、野木村さんご一家、間宮さんのお知り合いの草ヶ谷さん、草ヶ谷さんのお知り合いの島村さん(大川の集落支援員の方)、杉山さんの8名が、
18日は、水谷さん、間宮さん、草ヶ谷さん、山本さん親子、杉山さんの6名が参加しました。
古い障子紙を剥がして、こびりついた糊を取り除く作業に悪戦苦闘しながら、それでも2日間の作業で20枚ほど貼り替えることができました。
間宮さんのお知り合いの草ヶ谷さんが参加してくれたり、その草ヶ谷さんが声をかけてくださったのが、私たちも知っている大川の島村さんだったり、野木村さんの奥様とお子様2人が参加してくださったりと、人と人の輪が広がり、密になりました。
「清沢の家」を中心にしていろいろな可能性を予感させた2日間でした。
■12月17日(土)






■12月18日(日)








■完成




2011年12月18日
南側西角の押入れの天井
10月9日のブログ(http://kiyosawa.eshizuoka.jp/e815633.html)の最後で、
「南側西角の押入れの天井がまだ抜けたままなので(雨風は吹き込んでこない)、そのうち取りつけたいと思います。」
と書きましたが、
その作業を山本さん=1級建築士が行ってくれました。
この日は障子紙の貼り替え作業の日だったのですが、
水谷さんは山本さんを見るなり、
「山本さんの今日の仕事は、押入れの天井を作ることね」と
メチャブリしました。
山本さんいわく、
「材料も道具もないのに、どうやって・・・・・」
すると、水谷さんは、
「材料は、そこらにある廃材で、道具もそこらにあるものを適当に使って」と、
いとも簡単に言い放ちました。

山本さんは仕方なく作業に取りかかりましたが、
すぐに適当な廃材と切れないノコギリを見つけたようでした。

山本さんは、一人でコツコツと作業をしていましたが、他の人はみな障子の貼り替えで忙しく、誰も山本さんがどいう作業をしていたか見ていませんでした。

ところが、1時間ほどすると、「できました!」という山本さんの嬉しそうな声。
水谷さんが、「完成検査だ!」といって見に行くと、
「やっぱり、プロはすごいや!」と言いながら、すぐに帰ってきました。
山本さん、ご苦労様でした。

ただ、この作業が終わるとすぐ、
「次は壊れた障子の桟の修理ね」と、
またもや材料も道具もないメチャな作業を水谷さんから「指示」されていた山本さんでした。
重ね重ねご苦労様でした。
「南側西角の押入れの天井がまだ抜けたままなので(雨風は吹き込んでこない)、そのうち取りつけたいと思います。」
と書きましたが、
その作業を山本さん=1級建築士が行ってくれました。
この日は障子紙の貼り替え作業の日だったのですが、
水谷さんは山本さんを見るなり、
「山本さんの今日の仕事は、押入れの天井を作ることね」と
メチャブリしました。
山本さんいわく、
「材料も道具もないのに、どうやって・・・・・」
すると、水谷さんは、
「材料は、そこらにある廃材で、道具もそこらにあるものを適当に使って」と、
いとも簡単に言い放ちました。

山本さんは仕方なく作業に取りかかりましたが、
すぐに適当な廃材と切れないノコギリを見つけたようでした。

山本さんは、一人でコツコツと作業をしていましたが、他の人はみな障子の貼り替えで忙しく、誰も山本さんがどいう作業をしていたか見ていませんでした。

ところが、1時間ほどすると、「できました!」という山本さんの嬉しそうな声。
水谷さんが、「完成検査だ!」といって見に行くと、
「やっぱり、プロはすごいや!」と言いながら、すぐに帰ってきました。
山本さん、ご苦労様でした。

ただ、この作業が終わるとすぐ、
「次は壊れた障子の桟の修理ね」と、
またもや材料も道具もないメチャな作業を水谷さんから「指示」されていた山本さんでした。
重ね重ねご苦労様でした。
2011年12月11日
障子の貼り替え作業①
12月11日、この日は大掃除の手始めとして、障子の張り替え作業をしました。
といっても、この日の参加者は杉山さんと水谷さんだけで、30枚もある障子戸の張り替えの段取りを整えたり、ずいぶん前に貼られた障子紙をどのようにすればうまく剥がせるのかテストするのが目的でした。

障子戸を外した後、もとの場所に正確にはめ戻さないとうまくはまらなくなってしまいますので、ナンバーリングをします。

その後、1枚ずつ外して・・・・

まずは、障子に刷毛で水を塗りました。しばらく待った後、障子紙がうまく剥がれるとよかったのですが・・・・・
割り箸でかなりこすっても、やはりうまく剥がれませんでした。

そこで、水谷さんが持参のスチームクリーナーでたっぷりと蒸気を吹きかけて、その後でゴム製のヘラでこすってみると・・・・・
きれいにとれました。
この段取りで障子紙を剥がせばいいことを確認!

といっても、この日に障子紙を剥がした戸は3枚だけで、残りは本番の12月17日-18日にとっておきました。
その後、畑をちょって見て、この日の作業を終了にしました。
といっても、この日の参加者は杉山さんと水谷さんだけで、30枚もある障子戸の張り替えの段取りを整えたり、ずいぶん前に貼られた障子紙をどのようにすればうまく剥がせるのかテストするのが目的でした。

障子戸を外した後、もとの場所に正確にはめ戻さないとうまくはまらなくなってしまいますので、ナンバーリングをします。

その後、1枚ずつ外して・・・・

まずは、障子に刷毛で水を塗りました。しばらく待った後、障子紙がうまく剥がれるとよかったのですが・・・・・
割り箸でかなりこすっても、やはりうまく剥がれませんでした。

そこで、水谷さんが持参のスチームクリーナーでたっぷりと蒸気を吹きかけて、その後でゴム製のヘラでこすってみると・・・・・
きれいにとれました。
この段取りで障子紙を剥がせばいいことを確認!

といっても、この日に障子紙を剥がした戸は3枚だけで、残りは本番の12月17日-18日にとっておきました。
その後、畑をちょって見て、この日の作業を終了にしました。
2011年11月27日
柿渋とベンガラで塗装

今日は、漆畑さんが、床板を新しい杉板に取り替えた西奥南側の板の間の塗装をしてくださいました。
塗装材料は、日本古来の柿渋とベンガラという自然素材。
舐めても食べても大丈夫だそうです

一生懸命、作業をしてくださっています。

二度塗りをするとこうなります。
後日、この上に蜜蝋ワックスがけをするそうです。


塗料があまったので、縁側も塗装してくださいました。
漆畑さん、ご苦労様でした。ありがとうございました。
2011年10月09日
修繕作業 第2弾
9月23日までで床の修繕作業が終わったので、
10月9日に、その他で早急に修繕しなければならない個所を手当てしました。

まずは、南側手前と奥の2部屋の押入れの上に隙間がいていたので、
使っていない雨戸を切って、それを隠しました。

西側奥の雨戸が4枚中2枚しかなかったので、これも使っていない雨戸を加工してはめました。
また、雨戸の戸袋の板も破損していたので、はやり使っていない雨戸を打ち付けました。

先に修繕に利用した「使っていない雨戸」は、実は、囲炉裏がある北西側の部屋の天井板として使われていたものです。
かつて囲炉裏を使っていたときは、換気のために天井板はわざとなくしてあったと思いますが、囲炉裏を使わなくなったため、どこからか調達してきた雨戸を天井板かわりに屋根裏に敷いたのだと思います。
今回は、囲炉裏を復活させたので、その雨戸を取り払い、修繕に活用したわけです。

南西側に延伸されていた屋根のトタン板がかなり腐食していたため、採光のために取り払いました。
他にもちょこちょこ手を加えましたが、だいたいこんな修繕作業でした。
ちなみに、南側西角の押入れの天井がまだ抜けたままなので(雨風は吹き込んでこない)、そのうち取りつけたいと思います。
10月9日に、その他で早急に修繕しなければならない個所を手当てしました。

まずは、南側手前と奥の2部屋の押入れの上に隙間がいていたので、
使っていない雨戸を切って、それを隠しました。

西側奥の雨戸が4枚中2枚しかなかったので、これも使っていない雨戸を加工してはめました。
また、雨戸の戸袋の板も破損していたので、はやり使っていない雨戸を打ち付けました。

先に修繕に利用した「使っていない雨戸」は、実は、囲炉裏がある北西側の部屋の天井板として使われていたものです。
かつて囲炉裏を使っていたときは、換気のために天井板はわざとなくしてあったと思いますが、囲炉裏を使わなくなったため、どこからか調達してきた雨戸を天井板かわりに屋根裏に敷いたのだと思います。
今回は、囲炉裏を復活させたので、その雨戸を取り払い、修繕に活用したわけです。

南西側に延伸されていた屋根のトタン板がかなり腐食していたため、採光のために取り払いました。
他にもちょこちょこ手を加えましたが、だいたいこんな修繕作業でした。
ちなみに、南側西角の押入れの天井がまだ抜けたままなので(雨風は吹き込んでこない)、そのうち取りつけたいと思います。
2011年09月23日
床の修繕作業(2)

床の修繕作業2日目は、9月23日(秋分の日)に行いました。
19日に取り外して水洗いした床板をもとに戻し、真鍮クギで打ち付ける作業です。

真鍮クギはやらかいので、素人の私たちではすぐに曲がってしまいます。
ただ、建築士だけあって山本さんのカナヅチさばきは、正確で見事でした。

糸を目印にして一直線に打ち付けるのですが、板が反っていて、なかなかうまくいきません。
板が破損してしまっている個所もいくつかありました。

ふすまのレール部分の木(←これなっていうのかな?)がなかなかうまく元の位置におさまりません。
大工の梶山さんに手伝ってもらいました。
梶山さんは、床板の節の穴あき部分も部材でふざいでくれました。

私たちが担当した東側手前の2部屋と西側北奥の囲炉裏がある部屋の床板の打ち付けが終わりました。

西側南奥の部屋は、もとからあった床板がもう使いものにならなかったので、梶山さんに頼んで、新しい杉板をはっていただきました。
梶山さんの手さばき・身のこなしは、今日も快調。
みんなで、見とれてしまいました。

西側南奥の新しい床板も、(少し残っていますが)完成です。